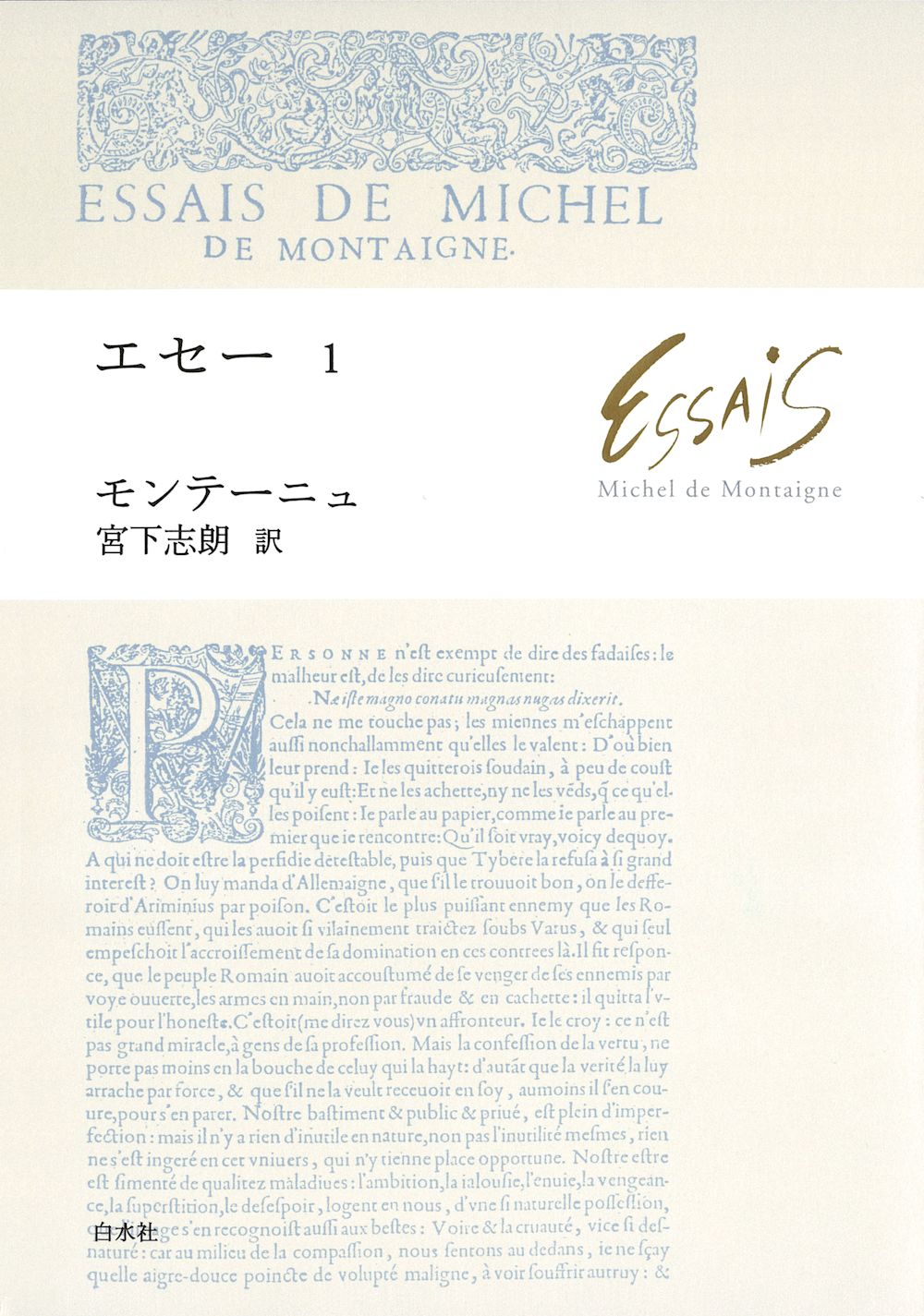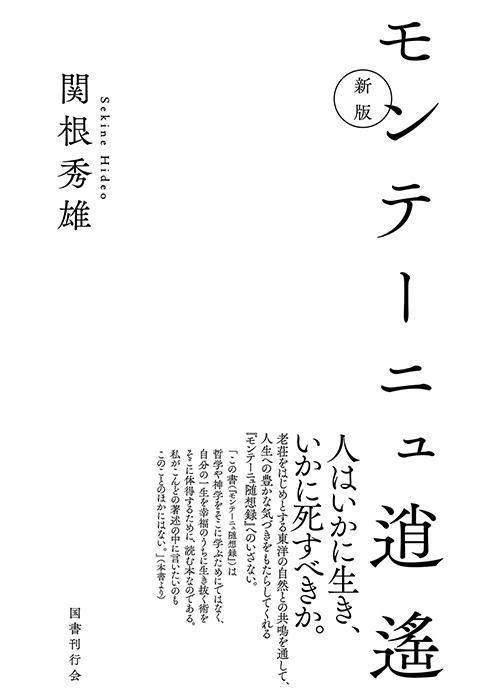時代が今、哲学エッセイを求める理由
Edited by
- 渡辺祐真作家・書評家・書評系YouTuber・ゲーム作家
はじめに
ここ数年、哲学にまつわるエッセイ(随筆)が数多く刊行されている。千葉雅也『センスの哲学』、永井玲衣『水中の哲学者たち』、三木那由他『言葉の展望台』など、話題になった本も多い。
いずれの本も、強固で取っ付きづらいイメージのある哲学や思想について、日常の題材と絡めて、やわらかく、親しみやすく綴られている。
今回はそんな哲学エッセイをいくつか紹介したい。
そもそもエッセイとは何か?
論理や議論によって積み上げられる堅牢な哲学と、心に浮かんだままを自由に綴るエッセイと、一見すると相反するように見える。
だが、語源をたずねると両者は一体だった。
エッセイの語源は、フランス語の「エセー(essai)」。これは、「試みる」を意味する動詞「essayer(エセイエ)」を名詞化したもの。
それを踏まえれば、エセー(essai)とは試みること、試行錯誤、思考実験、もっと平たく言えば「色々と考えてみること」を意味する。
つまりエッセイとは、書くことによって思考をめぐらせる実験室のようなものと言える。
書きながら考え、考えながら書く。一人で対話し、議論を積み上げていく実況中継と言えばわかりやすいだろうか。
だから、「心に浮かんだままを自由に綴ること」と、「論理や議論を積み上げること」がケンカせず同居している。
むしろそれらが同居し、協力し合っている場がエッセイと言える。
そしてその始祖が『エセー(随想録)』と名を冠せられた、思考実験書である。
著者は16世紀フランスを生きたミシェル・ド・モンテーニュ。
彼が約二十年間を通して書き続けたこの書は、日々の生活、人間の本性、古典文学など多岐にわたる題材について、自由に思索を展開している。
自由闊達で奥深く、知的でユーモラスな筆致は、現代に至るまで世界中に数多くの愛読者を産み続けている。
もちろん日本も例外ではなく、数々の『エセー』翻訳、モンテーニュ論、そして「『エセー』のエッセイ」などが生まれている。
2024年だけでも、海老坂武『生きるということ――モンテーニュとの対話』(みすず書房)、関根秀雄『新版 モンテーニュ逍遙』(国書刊行会)と二冊も刊行されている。(『新版 モンテーニュ逍遙』は、1980年に白水社から刊行されたものの再刊。)
前者は、モンテーニュの言葉を引きながら、深い連想や思索を展開していくもので、モンテーニュの入門としても、含蓄ある読み物としても面白く仕上がっている。
関根秀雄『新版 モンテーニュ逍遙』に学ぶ「エッセイの力」
『新版 モンテーニュ逍遙』は、生涯を『エセー』の研究と翻訳に捧げたフランス文学者による、本格的な「『エセー』論」であり、かつ「エッセイ」である。
その内容は、伝記や異本研究を積み上げた本格的なモンテーニュ論はもちろんのこと、『荘子』や『老子』、鴨長明、本居宣長や親鸞といったアジア思想との比較、神学から見たモンテーニュ、カミュやアランなど現代フランス文学とモンテーニュとの共振など、幅広い。
中でも骨子になっているのは、中国戦国時代の思想家である荘子との比較だ。その理由は次のように述べられている。
モンテーニュは、自分の書物は論説の部と物語の部から成っていると言ったが、『荘子』も全く同様で、構成の上でも両方はふしぎに互いに似通っている。格言があり詩があり問答があることまで両々相似ている。それらが深い哲学的思索の間に点在して、読者を緊張と疲労から救ってくれる。
P135
モンテーニュも荘子もどちらもひたすらに論を積み上げていくのではなく、様々なスタイルの言葉を織り交ぜることで、話題を展開していく。
現代的にいえば、対話的とも多声的とも言える文体だ。
では、モンテーニュはなぜそのようなスタイルをとったのか。
著者は、ある学者が江戸時代の思想家・本居宣長を評した「思想を思想という形では主張することを欲しない思想家」という言葉がモンテーニュにも当てはまるとした上で、次のように語る。
モンテーニュも宣長も、その目的とするところは、真理の追求にあった。自然とか神とか人生とか宇宙の法則とかの追求であったのだが、ただその追求は総括的言語によってではなく個別的言語によってなされねばならないと、二人ともに考えていたのであった。モンテーニュは生来抽象や理論や学説がきらいであった。彼は始めから総合の言語には不安がって、それを信用することができなかったからである。それよりも具体的な個々の言語に耳を傾け、歴史や伝記や民俗の中に生きた実例を求め、その上に〈哲学する〉ことに慣れていったのである。ひっきょうそのような日常茶飯の体験が彼の思想の内部に浸みこみ、彼にその追求する目的を捕捉させたのである。
P371〜372
ここにモンテーニュ『エセー』の、そして現代の哲学エッセイの求められる理由が凝縮されている。
高度な議論を基盤とした伝統的な哲学だけでは見えにくくなる個別性や日常性を拾い集めるために、エッセイという小回りの効く形式が役立つ。
自分の身の回りで起きた小さな出来事、歴史の中でひっそりと息をする小さな例外、それらに光を当て、そこから議論を立ち上げることにエッセイは長けている。
哲学×エッセイの精髄〜『世界の適切な保存』〜
ここまで述べてきた、思索、日常性、個別性の特徴を最も兼ね備えた哲学エッセイの書き手として、永井玲衣を挙げたい。
哲学対話という営みの旗手であり、冒頭にも挙げた『水中の哲学者たち』(晶文社)は15刷(2024年4月時点)という記録的な売れ行きだ。
永井は哲学を専門とするが、その文章の中には他愛もない日常や詩や短歌がのびのびと顔を出し、しかも結論めいたものも滅多に示されない。
彼女が考える様子が自由に綴られている。
そして、7月に満を持して二冊目の哲学エッセイ『世界の適切な保存』(講談社)が刊行された。
前著と同様、良い意味で肩の力が抜けた、のびやかで気持ちの良い思索や連想が連なり、時折ハッとさせるような結論や箴言に辿り着く。
結論ありきの押し付けがましさや、理論によって鎧われたようないかめしさもないが、気がつけば読者は著者と一緒に考えている。
個人的に特に印象に残ったのは「哲学モメント」と題された一編。
永井は、日常に潜む哲学的な瞬間として、「天気予報」を挙げる。その理由は、明日や一週間後という未来を予言する、人ならざる行為だからだと言う。
確かに、我々は日常的に天気予報や、それを支える科学に親しんでいるために、天気予報が未来を予言するという神秘さに無頓着だ。
永井はそんな当たり前にじっと目を凝らし、「あらゆる科学が発展した現代でも、なお人間が直接触れることのできない領域が「時間」なのだろう。だからこそ、時間に少しでも触れることができる営みは、どこか神めいている。」と、天気予報の特異性を炙り出す。
時間。
本来であればただ一定の速度で進むだけの存在なのに、我々はその時間を追い越して未来を見通すことができてしまう。
それこそが天気予報であり、そして、他者と交流することだと永井は言う。
対話の場では、ひとは互いの言葉をよくきいている。よくきくということは、それだけ他社がわたしの中に流れ込んでくるということだ。流れ込んだ他者を、わたしと出会わせて、言葉を見つけていく。そうすると、わたしの中の他者がうごめているのを見つける。なんとか引っ張り出して、少しずつその感触を確かめる。困難な作業だ。うろうろと視線がさまようように、語りもそこら中をうろつくことがある。
あちこちをさまよってしまうのは、話題や問いだけではない。過去なのか、未来のことなのか、いま考えているのか、語りは時間を飛び越えて、いろいろな場所を歩きまわる。それをよくきこうとすると、わたしたちもまた、そのひとの時間を生きることになる。
P114
精緻な論理展開では、天気予報と対話の間に橋を架けるには相当な議論が必要となる。なぜならあまりにかけ離れているから。
だが、永井はその二者を雲のようにふわりと結びつける。その雲の正体は、時に連想であり、時に短歌や詩であり、時に実感だったりする。
その足並みは自由だから、思いがけないところへ我々を導いてくれる。
永井の言葉は、哲学のような堅牢さと、詩のような軽やかさを併せ持っているのだ。
さいごに
現在は多様性の時代と謳われる。
様々な価値を尊重し、その中で言葉を紡ぐには、思いも寄らない価値観を想像できるような「大胆な客観」、そして自らの内に考えや思いを掘り当てる「慎ましい主観」が必要なのではないか。
私はこの二つの要素それぞれが、客観を重んじる哲学と主観から紡がれるエッセイに対応しているように思っている。
哲学エッセイには、客観性を広げつつ、主観を掘り下げる力がある。
Edited by
- 渡辺祐真作家・書評家・書評系YouTuber・ゲーム作家
同じ連載の記事一覧
書評家スケザネが選ぶ2024年3月の名品
小説『ここはすべての夜明けまえ』『宇宙人のためのせんりゅう入門』、ドラマ『虎に翼』について、書評家スケザネさんがこれぞという作品をご紹介します。
2024.04.25書評家スケザネが選ぶ2024年1月の名品
小説『シャーロック・ホームズの凱旋』『成瀬は信じた道をいく』のほか、ドラマ『光る君へ』など、書評家スケザネさんがこれぞという作品をご紹介します。
2024.02.26
書籍 特集の記事一覧
書評家スケザネが選ぶ2024年3月の名品
小説『ここはすべての夜明けまえ』『宇宙人のためのせんりゅう入門』、ドラマ『虎に翼』について、書評家スケザネさんがこれぞという作品をご紹介します。
2024.04.25書評家スケザネが選ぶ2024年1月の名品
小説『シャーロック・ホームズの凱旋』『成瀬は信じた道をいく』のほか、ドラマ『光る君へ』など、書評家スケザネさんがこれぞという作品をご紹介します。
2024.02.26世代を超え、国境を超え、愛され続ける『ハリー・ポッター』の世界を総まとめ!
映画『ハリー・ポッター』はもちろん、『ファンタスティック・ビースト』を含む「魔法ワールド」、そして原作小説も含めて、その魅力をおさらいします。
2023.07.18